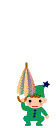 |
�������G������ |
 |
���v���T�����ɎQ��������A�������ɂP���B���N�Ԃ肩�ŁA������ɏo�Ȃ����B ��������w���Y�w���w�����ɂȂ��������搶�̍u�� �Ɨ��@�l�ɂȂ��āA���ꂩ��̐��Y�w���̒����ڕW�́E�E�E |
| �v���Ԃ�ɓ���b���B �����搶�́A���ƈꏏ�̓��w�������̂ɁE�E ���`��A�̂��l�ɂȂ��܂����I�I �F�ŁA�u���̊��z���E�E�E ��w����ƕ��݂ɂȂ��Ă����E�E�E�ƌ��������E�E |
 |
 |
���k �Q���҂������ԊF�N�z�ɂȂ��Ă��܂��܂����B ���ꂩ��Ⴂ�l���Q�����Ă����悤�ȁA������ɂȂ�悤�A�����̊撣��Ɋ��҂��܂��B |
�k��H�w�����w�n����������
�`��y���A���|�[�g���͂��܂����B�`
�u�����
�����F����17�N4��9���@14�F30�`19�F00
�ꏊ�F�w�m��فi���c��_�c�ђ�3-28�j
�L�F����8�� a-nakamura
�P�D�u���P�21���I�ɓǂ݂Ȃ����Ėڟ��Σ
�u�t�F���X�z��@�����w�@�������������ȋ���
�q�u�t�v���t�B�[���r
�k�啶�w�����a51�N���A����w�@���w�����ȓ��{�ߑ㕶�w��UMC�C���A�����w���������o�Č��E�A���Ό����̑��l�ҁA�����ɢ���̂Ƃ��Ă̕��ꣁi�}�����[�j�A��\���Ƃ��Ă̌�裁i�V�j�Ёj�A��̕��ꣁi�V�T�Ёj�A��ǂނ��߂̗��_��i�����A���D���[�j�A����Ό�����i�Ό���H�ƕҏW�A�ٗя��[�j�A�����ǂ݂Ȃ�����i�����ܐV���j
�q�u�����e�r
���w�����Ƃ̎����H�w���o�g�̊F����ɂ��b���Ƃ������Ƃň�a���������Ă����邩������܂���B���݁A��w�̐V�����ɓǂ��Ƃ̂��鏑�Ђ��Ɵ��̢�����룂����ʂɋ������܂��B��N�A��g���X�n��90���N���L�O���ēǏ��A���P�[�g��������Ƃ���1�ʂ���3�ʖ������ŁA�Ėڟ��͏��i�Ƃ��Ă�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̗F�B�ɑ�]���O�Y����Ђ��������܂����A���݂̔ޓ��Ɠ��l�ɁA��g���ɂɂ���V�����ɂɂ���A���ɂ͈����Ƃ���łɂȂ�����i������܂���B
�ߑ���{�ꕶ�̂͟������o�������̂ł��B������̔���g�t�i�c��3�`����36�j�A�K�c�I���i�c��3�`���a22�j�A�����t(����5�`29)���̕��̂��c�Â��Č����o�Ă��邭�炢�ł����A���i�c��3�`�吳5�j�ɂ͂����������Ƃ�����܂���B
���������ƂɂȂ����}�͓̂����Ƒ��ɖ{�Ђ��������V���i����40�N�A���u�t�������ē��Ёj�ł���A�ނ͐V���ǎ҂ɑ��ăT�[�r�X���_�����Ȃ��珬���������܂����B�������Ȃ������̓ǎ҂Ɉ��ǂ���闝�R�́A�ߑ���{�̍�ƂƂ��Ă͒��������N�ɂȂ��Ă��珬�������������Ƃ��������܂��B����g�t��25�ŕ��d�ɓo�ꂵ�܂������A��]���O�Y���l���o���ɖR�����w������ɏ����������Ă��܂��B����ɑ��ğ����f�r���[�����̂́A�����q�K����Â��颃z�g�g�M�X��ɔ��\�������y�͔L�ł��飂ł���A38�i����38�N�j�̂Ƃ��ł����B
��������܂łɂǂ������l���̌��������̂���H���Ă݂܂��傤�B���͕�C�푈���n�܂�1�N�O�̌c��3�N2��9���ɁA�]�ˋ����n�ꉺ�����i�V�h���v�䒬�j�ɉĖډƂ̌ܒj�O���̖����q�i�{���F���V���j�Ƃ��Đ���܂����B�s�v�c�Ȃ��Ƃɟ��̎�v�Ȑl���̐ߖڂƓ��{���o�����������̐푈�Ƃ̓s�^���Əd�Ȃ��Ă��܂��B��������i�Ėڏ����q�j50�A���ꂳ��i��}�j41�̂Ƃ��ł�����Ƃ�ł��Ȃ����N��o�Y�ł��ˁB�ĖډƂ͒�������ł������Ɖ^�͌X�������Ă���A1�̂Ƃ������V�h�̋撷������Ă����������V���̗{�q�ɏo����܂����B9�̂Ƃ��{�ꂪ�������ꂽ���߉����ƍݐЂ̂܂��Ƃ֖߂���܂��B����푈�̑O�N�i����9�N�j�ł��B�����ĉ������V���̂܂�20�܂ʼnĖډƂ���w�Z�֒ʂ��܂��B�����s�J�w�Z�������{��ꒆ�w�Z�������w�Ɂ������w�Ɂ���w�\����i��̈ꍂ�j�B
�ĖډƂł͒��Z�Ǝ��Z�����j�Ŏ���3�Z���\���������߁A���Ƃɏo���Ă������猋�j�̐S�z�͂Ȃ����낤�Ƃ������ƂŁA21�̂Ƃ��{���270�~���x�����ĉĖډƂɎ��߂���܂��B1�~������3��5��~�ɓ���܂������1�疜�~�Ŕ����߂��ꂽ��ł��ˁB���̓��e�͟��̎��`�I�����ƌ����颓�����ɏ�����Ă��܂��B���͂��̂Ƃ��c���Ȃ��Ţ���V����Ə������Ă��܂��B������P�ǂ݂���Ƣ���˂̂�������Ɠǂ߂��ł��ˁB����͔ނ��ꍂ����鍑��w�i���ȑ�w�p���w�ȁj�i�w�i����23�N�j���鍠�̂��ƂŁA�ːЏ�̖��͟��̃g���E�}�i���_�I�O���j�ƂȂ�܂��B
���͖���25�N�ɒ�����Ƃ�邽�ߌːЂ�����i����Ȃ��j�Ɉړ��������Ă��܂��B�F�����m�̐ϒO�����̕t�����ɂ��邱�̒��́A���ܢ�����Ėڟ��Η��Вn����ό��̔��蕨�ɂ��Ă��܂��B�k�C���ɂ͖����̏��߂ɓԓc�����u����A��A���n��J�s���Ă��܂����B�t�����e�B�A�Ƃ͐푈�̍őO�����Ӗ�����̂ł����A�����k�C�������ɂȂ�Ƃ������Ƃ͋��ɂ̒������ꂾ�����̂ł��B���͂��̂��Ƃɐ[�������������������܂��B���y�͔L�ł��飂̒��ɢ���i������j��Ƃ����Z�т�����������У�Ƃ����j���o�Ă��܂����A���̖����������̏؋��ł��B
����25�N�F�l�̐������i�̂ڂ�A����q�K��j�����j�Œ���ފw���V������{��ɓ��Ђ��܂������A���͒��p���w�ȑ��ƌ�A����28�N�Ɏq�K�̕�Z�E���R���w�i���Q���q�풆�w�Z�j�ɕ��C���Ă��܂��B���̂Ƃ��̂��Ƃ��������̂���V�����i����39�N���\�j�ł��B���̓����鍑��w�𑲋Ƃ��Ē��w�Z���@�ɂȂ�Ȃ�ĂȂ��������Ƃł����A�ނ͊O�l���t�g�܂肨�يO���l���t�Ɠ��������N�ŕ��C���܂�������A�Z����2�{�̋����i80�~�j�����Ă���̂ł��B���I�푈���̒鍑��w�̑��Ɛ��͑S����3�琔�S�l�ł�����A���� 1�w�N3��l�̓���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��G���[�g�Ȃ�ł��B���͗��N�i����29�N�j��܍����w�Z�փ��t�J�f�B�I�E�n�[���i���_�j�̌�C�҂Ƃ��ĕ��C���Ă��܂��B��Ƀ����h�����w����߂��Ă����Ƃ��i����36�N�j���n�[���̌�C�Ƃ��Ē��p���ȍu�t�ɂȂ��Ă��܂��B���̂���́A�����̕����J����S�������يO���l�̖�������{�l�Ɏ��߂��čs�����ゾ�����̂ł��B
����33�N�A�����Ȃ���p�ꌤ���̂��ߊ���w�𖽂����ă����h���֗������܂��B���̉p�����w����ƁE���ݏo�������v���ƂȂ����ƍl�����܂��B����34�N5�������q�K���ɏ������莆���A�q�K�͟��̋����Ȃ��ɢ�z�g�g�M�X��ɢ�ϓ֏����i���ǂ傤�����j��Ƃ��Ĕ��\���܂��B��ϓ֏�����Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����܂��B
��������֏o�Ă݂�ƈ����z�������z���F����ɔw�������B���܂��Ɉ��g�̂Ȃ�����肾�B����ȍ��ł͂�����Ɛl�Ԃ̔w�ɐł��������班���͌��������ȓ������ł��邾�낤���ƍl���邪�A����͏������ɂ��݂̌��炸���Ƃ����z�ŁA�����ȏ����������̕����ǂ����Ă����h���B���ƂȂ����������g�̋����S��������
���͐g����157cm�����Ȃ���������A���O���T�N�\�������h�Ȃ̂ɋ����Ă���̂ł��B�����ăV���[�E�B���h�E�ɉf���������̎p�����Ă��������܂��B����x�͌��������疭�Ȋ�F�������ꐡ�@�t�������ȂƎv���Ƃ��ꑦ���T���i���������j���g�̉e���p���ɉf�����̂ł���B��ނ������������ƌ������ł��������B����͗��̓��R����B
�_�[�E�B���̐i���_���X�y���T�[�iH.Spencer�A�p���̎Љ�w�ҁj���Љ�Ȋw�ɉ��p������Љ�i���_��͢����������Ȗ��J�����x�z����͓̂��R�ł��飂Ƃ����������@�̌n�Ɍ��т��܂������A���������p���l�̊፷������͉ߏ�Ȃ܂łɈӎ����Ă����̂ł��B
���̓������ď����ł́A�����푈�ɏ����������R�̓��{�l���U�߂Ă���Ƃ�������И_�i���������j�������Ă��܂����B���{�l�S�̂����Ђ����̂悤�Ɍ����Ă�����ł��ˁi�j�B�S�z���Ȃ��ʼn��������͈��Ђ����̋����Č����Ă���̂ł��B
���͏��ϓ֓��i���ǂ�Ƃ��j��̒��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B�2�N�̗��w��������x�ϓ֓��������������Ƃ�����B�c�s�����̂͒���܂��Ȃ������̂��Ƃł���B���̍��͕��p������A�n�����͂��Ƃ��m���B�܂�Ō�a��̓e�����{���̐^���֝e��o���ꂽ�悤�ȐS���ł�������B�܂���{�ɒu��������Ɛl�ԂƓe�̍����ƌ����Ă���̂ł��B��\�֏o��ΐl�̔g�ɂ�����邩�Ǝv���A�ƂɋA��D�Ԃ������̕����ɏՓ˂��͂��ʂ��Ƌ^���A���[�����S�͂Ȃ������B���̋����A���̌Q�W�̒���2�N�Z��ł�����킪�_�o�̑@�ۂ��A���ɂ͓�̒����n�C�ۂ̔@���ׂƂׂƂɂȂ邾�낤�ƁA�}�b�N�X�E�m���_�E�̑މ��_�����܂���̔@����S���Ǝv���܂�����������B
�}�b�N�X�E�m���_�E�iMax S. Nordau�j�̓h�C�c�̕]�_�Ƃőމ��_�idegeneration�j���������l�ł��B�_�[�E�B���̐i���_�͢������`�q�𓑑����ėD�ꂽ��`�q�������c�飑���������͊���ς��邱�Ƃɂ���Đ����₷��������飂ƍl���܂����A�މ��_�͈�����`�q�������c���čs���܂�����i���̋t�s�Ȃ�ł��ˁB�W�F���i�[�iE. Jenner�j�̎퓗�̓��N�`���i�R���j�̎g�p�ɂ���ĕa���ۂɑ���Ɖu����^���܂����A������މ��_���x��������̂ł��B
�p�����g�����X���@�[�����a���i���̓�A�t���J���a���j�̋��E�_�C�������h�z����_���ċN�������{�[�A�iBoer�j�푈�i1899�`1902�N�j�́A�����������̂̑�����������A��Ɍ���������A�t���J�A�M�̎哱���̓{�[�A�l�����邱�ƂɂȂ�܂����B�{�[�A�푈��w�i�Ƃ��āA�}�b�N�X�E�m���_�E�͉p���ő�x�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă����̂ł��B���݂ɍŋߖ���p���Ɉ��|��������~�D�i1984�`2004�N�j�̟��̊�͓����i�����j���C�������ʐ^�Ȃ̂ł��B
��ϓ֏�����i����34�j�ɖ߂�܂��傤�B�ނ͓��{�ƃ��V�A�̐푈�̊�@��\�z���Ď��̂悤�ɏ����Ă��܂��B��D�����Ɠ��{�͑����Ƃ��Ă͑����Ƃ�����B�x�߂͓V�q�o�̐J�߂�����B�p���̓g�����X���@�[���̋������@��o���ČR��̌��߂�Ƃ�����B���̑����Ȃ鐢�E�͒��ƂȂ���ƂȂ���]���g�p������ԂɁA��y�̏Z�ޏ��V�n�ɂ�����]�Ə��g�p�������āA�킪���h�̎�l���͂��̖c��Ȃ�g�̂�q���āA���̏����ҍ��z�Ǝ��Y��������Ƃ�����B�������Č�y�͎q�K�̕a�C���Ԃ߂��߂ɂ��̓��L���������飁B
��V�q�o��Ƃ͓V�q���{�a�̊O�Őo�����������Ԃ�i�ώ��ɍۂ�����j���Ƃł��B�����h���̉��h�́ATV�̃V���[���b�N�z�[���Y�ɂ��o�ė��܂����A�؎傪�t���A���ɏ��L���鎝���t���A���ł����B���̉��h�̒��Y�K���̑�Ƃ��j�Y���ĉƍ��������������������̂ŁA���h�l�ƈꏏ�ɖ铦���������ł��ˁB�����̉p���̖@���͓��̏o������̓��܂ł����K�p���ꂸ�铦�����Ă���߂��Ȃ������̂ł��B�܂����͏��ߌ��z�w��ڎw�������n�̓��]�̎�����ł�����A�C�̔g�͒n���̎��]�ƌ��̌��]�Ƃ̊W�ŋN���Ă��邱�Ƃ�A��]�^���͂ǂ̔�������������Ă���]�^���ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��܂����B���ꂪ�����]�Ə��g�p��Ƃ������t�ŕ\������Ă���̂ł��B�H�w���̊F����ɂ����̂��������܂����ł����A�R�[�q�[��~���܂킵�ă~���N����H���炷�ƁA�ǂ̕����ɂ��~���N�̏����ȉQ�������ł��Ă��邱�Ƃ�����ł��傤�B
�����p���֗��w���������i1900�N5���`1902�N11���j�͑�p�鍑���Ȃ肪�o�Ă������ŁA���̊C���x�z������p�鍑�̃��B�N�g���A�������S���Ȃ����̂�1901�N�ł��B20���I�����ɂ�����p���̖v���̖G�������������́A���I�푈�i1904�`05�j�ɏ����ė̒��ԓ��肵�����{�̏�����\�����Čx����炵�Ă��܂��B���Ȃ݂ɢ20���I��Ƃ������t����{�ɓ��������̂͟��ŁA������O�l�Y�i����41�j�̒��Ŏg���Ă��܂��B
�����鍑��w�p���ȍu�t�i����36�`39�j�̂Ƃ����\�����̂��������ł��B��l�̐��m��Ƃ���B�̓ߌÈ�Ƃ��������K�ˁA�o�߂�̓ߔ�����Ƃ��������Ɖ���ĊG�ɕ`�����Ƃ��邪�A�ޏ��̊�ɂ͗��ꂪ�����Ă��邽�߉悯���ɔY�ނƂ����A�e�͂ǂ��Ƃ������Ƃ̂Ȃ��b�ł��B���̏I��߂��̎��̈�߂����̋ߑ㕶���ᔻ�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B
����悢�挻�����E�ֈ�������o���ꂽ�B�D�Ԃ̌�����Ƃ�����������E�Ƃ����B�D�Ԃق�20���I�̕������\������̂͂���܂��B���S�Ƃ����l�Ԃ����l�߂č��ƒʂ�B��e�͂͂Ȃ��B�l�ߍ��܂ꂽ�l�Ԃ͊F�����x�̑��͂œ���̒�ԏ�֎~�܂��āA�������ē��l�ɏ��C�̉���ɗ����˂Ȃ�ʁB�l�͋D�Ԃ֏��Ƃ����B�]�͐ςݍ��܂��Ƃ����B�D�Ԃقnj����y�̂������̂͂Ȃ��B�����͂��������̎�i��s���Č��B�����߂����A���������̕��@�ɂ���Ă��̌��݂��悤�Ƃ��飁B
����͍�����99�N�O�ɏ����ꂽ���͂ł��B�D�Ԃ͋ߑ㕶���ł��荑�Ƃł��B�S���鍑��`�̍��Ƃ͌l�a�ȏ�Ԃɒu���ƌ����Ȃ���A���͔j�ł̐푈�֓����čs���Ƃ̂��Ƃ������Ƃ���͎��̂悤�ɗ\�����Ă��܂��B
���l�O���؉������̒n�ʂ�^���āA���̒n�ʂ̂����ł͐Q��Ƃ��N����Ƃ�����ɂ���Ƃ����̂������̕����ł���B�����ɂ��̉��؉����̎��͂ɓS���݂��āA�������ւ͈�����o�Ă͂Ȃ�ʂ��Ɗd�����̂������̕����ł���B���؉����̂����Ŏ��R���ق����܂܂ɂ������̂��A���̓S��ȊO�ɂ����R���ق����܂܂ɂ��������Ȃ�͎̂��R�̗��ł���B����ނׂ������̍����͓���ɓS��Ɋ��ݕt���ę��K���Ă���B�����͌l�Ɏ��R��^���ČՂ̂��Ƃ��҂��炵�߂����A�����B�v�̒��ɓ�������œV���̕��a���ێ�������B���̕��a�͐^�̕��a�ł͂Ȃ��B�������̌Ղ������l���ɂ߂ĐQ�]��ł���悤�ȕ��a�ł���B�B�̓S�_����{�ł���������A���͂߂���߂���ɂȂ�B���̃t�����X�v���͂��̎��ɋN����̂ł��낤�B�l�̊v���͂��܊��ɋN�������B�k���̈̐l�C�v�Z���͂��̊v���̋N����ׂ���Ԃɂ��ĂԂ��ɂ��̗����l�ɗ^�����B�]�͋D�Ԃ̖җ�Ɍ����Ȃ��S�Ă̐l���ݕ����l�ɐS���đ���l������x�ɁA�q�Ԃ̂����ɕ����߂�ꂽ��l�ƌl�̌��ɐ��|�̒��ӂ����ɕ��킴�邱�̓S�ԂƂ��r���āA��Ȃ���Ȃ��A�C�����Ȃ���Ί�Ȃ��Ǝv���B����̕����͂��̊�Ȃ��ŕ@��˂���邭�炢�[�����Ă���B�������^���Âɖӓ�����D�Ԃ͊�Ȃ��W�{�̈�ł���B�
�C�v�Z���iH.Ibsen�j�͏����̉�����������m���E�F�[�̌���ƂŁA�����������\����1906�N�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B�m���E�F�[�͂��ăX�E�F�[�f���ƃf���}�[�N�̑����ŁA1905�N�ɕ����Ɨ�������A�m���E�F�[�̍����͍��Ƃ̔������悤�ɂȂ�܂����B�����B�͍��Ƃ̔�����Ȃ��C���N���̑��̍����ɑ��Ăǂ̂悤�Ȏ�������ׂ悤�Ƃ��Ă���̂ł��傤���B
�Q�D�u���Q��z�E�f�������i�L�@�{�����_�j�̍������w�
�u�t�F�{�Y���v�@�k���w�@�H�w�����ȋ���
�q�u�t�v���t�B�[���r
�k��H�w���������w�H�w�ȏ��a44�N���A����w�@MC�C���B�C���f�B�A�i��w���m���������o�Č��ݖk���w�@�ŗL�@�H�Ɖ��w�u����S���B����7�N�x���{���w��w�p�܂���܁B�{�Y�搶�͗�؏͖��_�����i����16�N�x�w�m�@��܁j�̋��������҂Ƃ��ė�J�b�v�����O����������ȂǗL�@�z�E�f���w������J�ꂽ�B���݂͗L�@�����������𗘗p����V�����L�@���������A�G�}�v���Z�X�̊J���ɏ]���B
�q�u�����e�r
�@��J�b�v�����O����
�EPd�G�}��p���ėL�@�n���Q�������ƗL�@�z�E�f�����������т���N���X�J�b�v�����O�����ŁA�R����܂�G�C�Y������A�t���̐������Ɋ��p�����ȂǗL�@�������w��ޗ����w���̍L������ɑ傫�ȉe����^�����B
�E��؏͋�����1979�N�ɕ��A�gSuzuki Coupling Reactions�h�Ƃ��Đ��E�ɒm���邱�̔����͈��i���܂ސ��X�̐��������V�R�������ɗ��p����A���ɊC�Y�ŁgPalytoxin�h�̑S�����̍ŏI�H�����\�ɂ������ƂŐ��E�I���ڂ𗁂т��B�܂��A���[���^�{�����_�̃J�b�v�����O������p����r�A���[���������̍����@�́A�ߔN���ڂ���Ă���F�����n�@�\�������q��ޗ��J���ɑ���̍v�����ʂ������B
�E�A���[���{�����_�͐����C�Ɉ���Ŏ�舵���₷�����ƁA�܂������G�}�����A�I�𐫂��ʐ���L���Ă��邱�Ƃ���A���i�E�@�\�ޗ��̒T�������⓱�d�������q�ALED�ȂǕ��q�v�Ɋ�Â������n�����q�ޗ��̊J���L���\�ɂ��A�ă����N�Ђɂ����錌���~����Losartan�A�ƃ����N�Ђ�`�b�\���ɂ�����t���ȂǍH�ƓI�X�P�[���ł̐����@�ɂ��̗p����Ă���B
�A��؏͖��_��������
�E ���a34�N�k�嗝�w�����Ȕ��m�ے��C���A���a36�N�H�w���������w�H�w�ȏ������A���a48�N���p���w�ȋ����A����6�N�ފ��A���̌㉪�R��w�����A�q�~�|�p��w�������C�B
�E ���a38�N����2�N�ԕ�Purdue��wH.C.Brown���������m�������Ƃ��ėL�@�z�E�f�������̍����Ɨ��p�Ɋւ��錤���ɏ]���A�A���ケ�̕�����X�ɔ��W�����Đ��E�����[�h���鑽���̑�z�����Ɛт��������B
�E �����̋Ɛтɑ���1986�N��Weissberger-Williams Lectureship Award�A1987�N�؍����w����J�܁A1989�N���{���w��܁A1995�N�č�Dow Elanco Lectureship Award�A2000�Nthe
H.C.Brown Lecture Award(��Purdue��w)�A2001�NThe Distinguished Lecture Award(��Queens��w)�A2004�N�L�@�������w���ʏ܁A2004�N���{�w�m�@�܂���܁B2005�N�x�m�[�x�����w�܍ŏI�I�l�Őɂ������킷�B
�B�q�h���z�E�f�������iHydroboration�����j
�E��J�b�v�����O�����́A�r�j���^�z�E�f�������ƗL�@�n���Q��������Pd�G�}��p���ăN���X�J�b�v�����O�����u���I���t�B�����������锽���ŁA�r�A���[���̍����ɂ͂��̔������悭�p������B�r�j���z�E�f�������̓A�Z�`�����̃q�h���z�E�f�������ɂ�荇���ł���B
�E�q�h���z�E�f�������Ƃ̓z�E�f�ɗL�@������锽���ŁA�s�O�a�����Ƀ{�����i�z�E�f�̐��f�����j���t�����āA�A���L���{�������������锽���B
��C=C���{H-Br���@���@R-CH=CH-B��
�C�N���X�J�b�v�����O�����iCross Coupling Reactions�j
�@�E�L�@�������w�ɂ����ĈႤ���j�b�g���m��I��I�Ɍ��������锽��
�E���`�ɂ͗L�@�����������ƗL�@�n���Q�������Ƃ�J�ڋ����G�}�̑��݉��Ŕ��������AC-C�����������锽�����w���B
Cat.
R-m�{R�L-X�@���@R-R�L�{m-X
Cat.
R-CH=CH- m�{X-CH=CH-R�L�@���@R-CH=CH- CH=CH-R�L�{��-X
|
�� |
�G�} |
�J�b�v�����O���� |
|
MgX�L |
Ni �G�} |
�F�c-�ʔ�-Coriu�J�b�v�����O |
|
ZnX�L |
Pd�G�} |
���݃J�b�v�����O |
|
SnX�L |
Pd�G�} |
����-�E�c-Stille�J�b�v�����O |
|
Bn(OH)2 |
Pd�G�}/���� |
���-�{�Y�J�b�v�����O |
|
SiR X�L |
Pd�G�}/F |
��R�J�b�v�����O |
�D�L�@�z�E�f������(�L�@�{�����_)��p�����N���X�J�b�v�����O�����i1979�N�ɖk��̗��-�{�Y��ɂ���Ēa���j
�r�j���^�{�����_��p�����W�G�������i�L�@�{�����_�݂̂ł͋��������ߒ��̃X�e�b�v�͐i�s���Ȃ�������̑��݉��Ńz�E�f�����������邱�ƂŐi�s����j
Pd(PPh3)4
�q-CH=CH-B(OH)2�{Br-CH=CH-R�L�@���@R-CH=CH-CH=CH-R�L
�E�A���[���{�����_�ƃn���Q�����A���[������Pd��������p���ăr�A���[���iBiaryl�j�����������������J�b�v�����O����
Pd������/Na2CO3
R-��-B(OH)2�{X-��-R�L�@���@�@R-��-��-R�L
�F���p��
��J�b�v�����O�������p�e���g�����Ȃ��������Ƃ͓Ɨ��@�l�k��̍ő�̎��s��ƌ����邱�Ƃ����邪�A�p�e���g�����Ȃ��������ߋZ�p����Ђɖ��炸�S���E�ʼn��p���ꂽ���Ƃ͐����������ƕ]������Ă���B
�E�{���r�R�[���iBombycol�j�i�\�̐��z�������j�̍���
�E�p���g�L�V���iPalytoxin�j�i�C�\�M���`���N�ނ��܂ޓŁj�̍���
�E��BASF�А�Boscalid�i��̎E�ۍ܁j�̍���
�E�r�A���[���������̃����|�b�g����
�E�F�����{�����_�G�X�e���A�r�j���^�{�����_�G�X�e���̍���
�E�����n�����q�ޗ�
�|���p���t�F�j�����A�|���s���[���A�|���t�F�j�����r�j����
�E�t���A�L�@EL���̋@�\���ޗ��̒T�������E�����@
�E�_��A���̒T������
�R�D�k��ߋ��i���p���w�R�[�X��U���@�s��P�������j
�P�j�Ɨ��@�l���ʼn����ς�H
�@���������팸
�A��ʉ��B�����̉^�c�ɂȂ���
�B�����Ȋw�Ȃ̈ӌ��ɕq���ɂȂ���
�E�Y�w�����̐��i�A��w�ɂ��N��
�E�����擾�̐���
�E�O�����������̊l��
�E�C�����x�̓���
�E���m�ے��w���̏[���i�[�����Ȃ��ƒׂ����Ƃ��������j
�Q�j���m�ے��w���̏[���i���17�A8���j
�E�Љ�l���}����
�E�C�m1�N�Ŕ�ы����w
�E���m2�N�ő��Ƃ�
�R�j�|�v�����ؕ���
�E2004�N9��8���̑䕗18���i����50��/�b�j�œ|�ꂽ�|�v�����������颖k�C����w�|�v�����؍Đ��x���࣌�����2,000���~���W�܂����B
�E���R�������V�|�v������A��
�S�j�H�w�����w�n�w�Ȃ̗��j
|
�吳13�N9��25�� |
�k�C���鍑��w�ɍH�w���ݒu |
|
���a14�N4��11�� |
�R���H�w�Ȑݒu |
|
���a17�N4�� 7�� |
���Y����H�w�Ȑݒu |
|
���a21�N3��20�� |
�R���H�w�Ȃ����p���w�Ȃɉ��� |
|
���a24�N5��31�� |
�V���k�C����w�H�w���E���p���w�ȁA���Y����H�w�� |
|
���a35�N4�� 1�� |
�������w�H�w�Ȑݒu |
|
���a46�N4�� 1�� |
���Y����H�w�Ȃ������H�w�Ȃɉ��� |
|
���� 6�N6��24�� ��w�@�d�_���ɔ��� ���g |
3�w�ȁi�����E�����E�����j��2�w�ȁi���p���w�ȁA�ޗ��H�w�ȁj�ɍĕ� |
|
�H�w������3��U�i�����A�����A�����j��2��U�i���q�H�w��U�A�����H�w��U�j�ɍĕ� |
|
|
����17�N2��15�� |
���p���w�ȁA�ޗ����w�H�w�Ȃ����p���H�n�w�ȂɍĕҁB�H�w����4�w��16�R�[�X15��U�ƂȂ�B |
�T�j�H�w�����p���H�n�w�ȂƑ�w�@�H�w�����ȂƂ̊W
|
�H�w�� ���p���H�n�w�� |
��w�@�H�w������ �i�C�m�E���m����ے��j |
|
���p�����H�w�R�[�X |
���p�����w��U |
|
���p���w�R�[�X |
�L�@�v���Z�X�H�w��U �����@�\�����q��U �������w��U |
|
���p�}�e���A���H�w�R�[�X |
�ޗ����w��U |
�U�j���p���H�n�w�ȉ��p���w�R�[�X�����w�i�ΐ��F�{���o�Ȏҁj
|
��U |
�u�� |
������ |
���� |
������ |
|
�L�@�v�� �Z�X�H�w ��U |
�L�@�H�� ���w�u�� |
�L�@�������w |
�{�Y���v |
�ΎR���� |
|
�����L�@���w |
���@���� |
��k�v�T |
||
|
�L�@�������w |
��F�@�B |
|
||
|
���w�H�w �u�� |
���w�V�X�e���H�w |
���c���v |
�ҏr�Y |
|
|
�ޗ����w�H�w |
���M�v |
�����s�� |
||
|
���w�����H�w |
�r�䐳�F |
���암��p |
||
|
�����@�\ �����q��U |
�����H�w �u�� |
�Đ���ÍH�w |
�������M |
�c������ |
|
�זE�|�{�H�w |
���@�r |
�b�Ǔc�m�� |
||
|
�o�C�I���q�H�w |
�c������ |
���r�F |
||
|
���q�@�\ ���w�u�� |
�����q�@�\���w |
�o�m�L�� |
�c������ |
|
|
�����v�����w |
��ږ��v |
�J���� |
||
|
���q�ޗ����w |
- |
�����M��Y |
||
|
�������w ��U |
�@�\�ޗ� ���w�u�� |
�d�q�ޗ����w |
�s��P�� |
����@�� |
|
�ޗ��@�\���w |
����p�� |
����_�� |
||
|
�E�ʓd�q���w |
�������_ |
���Z�a�v |
||
|
���@�ޗ� ���w�u�� |
�\�����@���w |
�g��M�� |
�c���h�� |
|
|
�ő̔������w |
���c�u�Y |
���F�� |
||
|
���@�ޗ����w |
�������� |
�y�c�@�� |
�ȏ�